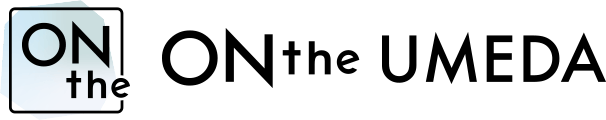「介護は究極のサービス業」天職で日本とアジアの架け橋をめざす。
ONtheに関わる人々、利用する会員様にスポットを当ててその人生に迫るインタビュー特集「穏坐な人々」。今回お話を伺ったのは、介護福祉講師と日本語教師の二足の草鞋を履いて活躍する松本 真奈美さんです。介護に対する想いや、幼少期から抱いていた夢の話を伺いました。
インタビュアー / RINO
- 介護福祉講師×日本語教師 / 松本 真奈美(まつもと まなみ)
- 大阪生まれの奈良育ち。介護福祉講師と日本語教師の2つの顔を持つ。介護教育を日本国内だけでなく、アジアの国々に広める目標を掲げ、活動中。歴史ある建物が好きで、現在は築100年の長屋暮らし。趣味は古い町並みの散策、寺院仏閣巡り、骨董市に並んだミニアンティークグラス集め。
介護福祉講師×日本語教師で活動中

現在松本さんは、インドネシアやミャンマーなど、アジアの国々からやってきた技能実習生たちに、介護福祉の指導や日本語を教えている。
文化の異なる彼らに、なぜ介護を教えているのか、きっかけは幼少期に見たテレビCMだった。
CMで流れたワンシーン いつしか自身の夢に
「発展途上国で日本人男性が、ただ井戸を掘るCMがとても印象的でした」
水不足で悩んでいる現地の人たちと協力し、男性が黙々と井戸を掘り続けるCM。湧き出た水を美味しそうに飲むシーンは、幼い松本さんの目には鮮烈に映った。
いつか現地に行ってみたいと潜在的に感じていた日々に、転機が訪れたのは大学生のころ。奈良県青少年課海外協力事業が募集していた「インドネシアの植林のための土壌作りと植林」のポスターに目が留まった。
「私が参加しても現地で役に立つかわからない。それでも、小さい頃見たあの光景を見たかったんです」
不安と期待を胸に抱きながら、初めて海外支援に訪れた国はインドネシア。貧しくもたくましく生きる人々の表情や慈しみ合う姿に、こんな世界があるんだなと強く思ったという。ボランティア活動をしていく中、NGO団体のスタッフと知り合い、帰国後も一緒に活動しないかと打診され、所属を決める。インドで学校や病院を建設するプログラムに関わり、国内で資金を集めるためにチャリティーコンサートやバザーのスタッフとして働いた。
あるコンサート終わりの打ち上げで、NGO団体の事務局長の発言に運命的なものを感じた。
「昔な、関西テレビの番組内で海外支援のCMを流していたんや。ちなみに井戸掘ってたの息子やねん」
幼き日に見た夢、目標を与えてくれた人物との出会いに松本さんの胸はいっぱいになった。その様子を見た局長から大学を卒業したら、インドの学校で、日本語を指導するボランティアをしてみないかと誘われ、二つ返事で承諾。
そこから5か月間、インドでホームステイしながら、現地の子どもたちに日常的な日本語を教えた。NGO団体に所属する一方、松本さんは大阪でホテルのフロントクラークとして働きながら日本とインドを行き来していた。
ボランティア活動を通して、現地の人たちと仲良くなり、今でも定期的にホストファミリーと連絡を取り合っている。
介護を通じて見えた「究極のサービス業」

2006年に結婚を機にボランティア活動を休止し退職。地方に移住する。
自然豊かな地域は選べる職が少なく、ひとまずはレストランのホールでパート勤務を始めた。しかし、客足は少なく勤務時間をカットされる日々が続いた。季節が3巡したある日、求人情報で見つけたのは「特別養護老人ホームの介護ヘルパー」の仕事だった。
収入面の安定を図るため、転職を決意。ヘルパー2級の資格を取り、いざ入職する日、新入職員挨拶もそこそこに先輩に案内されたのは霊安室だった。そこには、眠っているご利用者さまの姿があった。
「私が勤めることになった特別養護老人ホームでは、ご希望があれば最後のご葬儀も行えたんですね。初めての仕事は眠っているご利用者さまへの挨拶、出棺のお手伝いでした」
入職してすぐに辞めてしまう職員もいる中、日々の業務を淡々とこなしていった。最初は安定した収入のために始めた仕事だった。ご利用者さまの体をふき、ご飯を用意する。時には話し相手になったり、自身の悩みを相談したりする中で、いつしか松本さんの心にはある想いが芽生えた。
「介護は、肉体的・精神的につらいことも確かにありますが、ご利用者さまの生活を、ただお手伝いするだけではないんです。最期の瞬間に立ち会って笑顔でお見送りできるんです。介護は、ホテルやレストランのお客様をもてなすサービスとは異なり、人の尊厳に寄り添う愛に溢れた究極のサービス業だと気がついたんです」
介護職に就く未来を想像していなかった松本さんにとって、介護職が「天職」になった瞬間だった。さまざまな研修を受け始めて、国家資格である介護福祉士の資格を取得したころには、4年の月日が流れていた。
紆余曲折した3年間、職員との意見の対立に悩んだ松本さんが選んだ道とは?

介護に喜びを感じていた松本さんだったが、プライベートでは、2021年に15年間の結婚生活に終止符を打つ。一人で生活していくためには、収入を上げる必要があり、介護福祉講師に転職。
2023年にはグループホームで介護職として復帰し、ご利用者様のお世話と後輩や海外技能実習生の指導を兼任する。
しかし、介護に対する知識や経験、自身の想いを伝えていくうちに意思疎通ができなくなっていく。スタッフとの意見の対立や、業務負担が増えてしまい、次第に精神的に追い詰められていった。
「人員不足で業務効率を優先する職員、こだわりを持った職員同士で介護方法を主張しあい、足並みがばらばらになってしまいました。私が積み上げてきた経験が活かせない、介護が苦痛だと感じられるほど追い詰められていました」
理想的な働き方ができず、仕事を辞めることを考えた。前にも後ろにも進めない中、松本さんはふとあることに気がつくのだ。
仕事に必要な基本的な知識や技術を習得する介護初任者研修を修了しており、介護福祉士になって5年以上の実務経験がある。勤め人でなくても介護職員に対して、専門的な講義ができる立場にいたのだ。
そこからの松本さんの行動は早かった。思い切って退職し、フリーランスとして指導する道を選ぶ。また、以前から関わっていたアジアからやってくる海外技能実習生の指導を、本格的に仕事にすることも同時に考えていた。
介護現場で働く外国人技能実習生が、日本語の壁に苦しみながら仕事を覚えようとしている姿を見て、言葉を正しく伝えることの重要性を改めて痛感していたからだ。
「彼らに介護技術を教えるには、日本語の指導が欠かせません。でも、それ以上に、文化や価値観の違いを理解し、どうすれば日本の考え方を伝えられるのかが大きな課題でした」
フリーランスで働く傍ら松本さんは、日本語教師の資格取得を決意する。Instagramに勉強記録を残し、時にはくじけそうになる自分自身を鼓舞。勉強を始めて430日目、ついに合格を果たした。
人との積極的な交流ができる「ONthe」
「現在、親や配偶者の介護する立場の人がどのようなことで悩み、不安に感じているのかを知りたいと思い、情報収集と交流の場として活用しています」
東梅田から徒歩3分の好立地にある「ONthe」は、異業種や地方に住む人とも出会い、繋がれる点も魅力的だと感じている。
また、松本さんは月1回『かいごcafe』という交流会を開催。毎回介護職のスペシャリストをゲストに呼び、現在介護で悩む人、これから携わる人たちが気軽に不安や疑問などが聞ける場を設けている。
「大切な人や自分を守るため、正しい知識を身につけてもらいたい。気軽にお立ち寄りください」
正しい介護の知識を日本とアジアに広めたい

「アジアの国々でも高齢化が進み、介護施設が建設されています。しかし、現地の人たちは一昔前の日本のように、家族は自分で看るのが当たり前だと思っているんです」
ベトナムでは、すでに高齢化が進んでいる。老老介護や、ヤングケアラーといった問題に直面する未来は遠くないという。松本さんは日本とアジアに拠点を置きながら、活動を視野に入れている。現地で介護体制の土壌づくりを行いながら、日本国内では技能実習生が母国でも介護ビジネスや、講師として活躍できるような教育を提供する。
技能実習生の受け入れ態勢についても、変えていきたいと松本さんは話す。
「介護現場で外国人と働く日本人職員が言語のストレスを感じています。人員不足で苦しむ現場のストレスを少なくするコミュニケーションの手段として「やさしい日本語」を介護現場に伝えたい。介護サービスを維持するためにも、日本人と外国人をつなぐ共通言語が必要です」
また、介護に携わっていない人にも、現場の雰囲気を知ってもらうためにInstagramを発信。
「実際、お世話しているご利用者さまとの触れ合いの中で、思わず“にやり”と笑ったり“ほっ”と癒されたりするお話を紹介しています」
幼い日に見た日本人男性が井戸を掘る姿は、松本さんの今につながっている。
「海外に行っても何ができるかわからなかった私でしたが、今は天職である介護を通じてアジアに住む人たちを支援したい」
まっすぐと前を向いた松本さんの未来はきっと明るいはずだ。
編集後記
さわやかな笑顔が印象的だった松本さん。話を聞いて、私の中にあった介護に対する印象が180度変わりました。世間やネットニュースで言われているようなネガティブなものではなく、心を震わす人間ドラマがあり、愛と慈しみに満ちているのものだと感じました。
松本さんのInstagramでは、そんな介護現場の様子が紹介されています。読み進めていくと胸が温かくなって思わず“にやりほっと”してしまいます。
個人的に好きなのは「旅立ち」と「かれし」のお話です。一人ひとりの介護に対する認識が温かいものに変われば……と思わずにはいられませんでした。
松本さんのInstagramは、下記URLよりお読みいただけます。
https://www.instagram.com/niyarihotto/
(執筆:RINO、撮影:今井 剛)